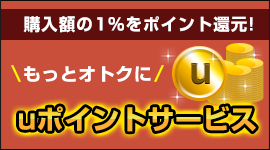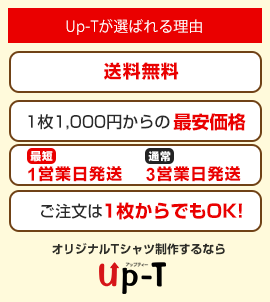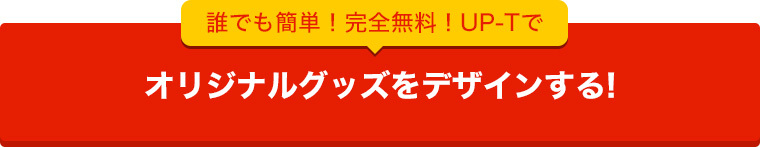最終更新日: 2024年09月25日
のぼりと旗の違いは?のぼりの定義や歴史を徹底解説!

お店の店先などでよく見かける「のぼり」。
形状としては旗によく似ていますが、なぜのぼりは旗ではなく「のぼり」と別の名称で呼ばれるのでしょうか。
この記事では、のぼりと旗の違いやのぼりの歴史、のぼりの広告効果などについて詳しく解説します。
のぼりと旗の違いは「用途」と「固定されている辺の数」

「旗」は、「布や紙を竿の先につけて掲げるもの」とされています。
よく似たものに店先などで広告として使う「のぼり」があります。
のぼりは、旗と同じように見えるものですが、以下のような違いがあります。
【旗とのぼりの違い】
- 用途が違う
- 固定されている辺の数が違う
- 素材が違う
旗とのぼりの違いを詳しく見てみましょう。
用途が違う
のぼりと旗の違いの1つに、用途があります。
のぼりはお店やイベントなどで、広告宣伝のために使われるものです。
横長の形が多い旗に対し、主に縦長で作られるのぼりは文字入れがしやすいという特徴があります。
お店のキャンペーンなどアピールするのにある程度文字数が必要な場合でも、のぼりであれば効率的に宣伝することが可能です。
一方、旗は国旗のように何かのシンボルとして扱われるアイテムです。
旗の用途は宣伝ではなく、国や団体・チームなどの統率や士気を高めるためのものであるケースが多いようです。
固定されている辺の数が違う
のぼりと旗とでは、固定されている辺の数が違います。
竿に対して一辺だけが固定されている旗に対し、のぼりには乳と呼ばれる輪がついており、二辺で支える場合がほとんどです。
のぼりは固定される辺が二辺になっているため旗より翻りにくく、印字された文字が読みやすくなっています。
素材が違う
のぼりは、安価で大量に作れるポリエステル素材が使用されるケースがほとんどです。
広告宣伝を目的に作成されるのぼりはお店のキャンペーンが終わるなどして宣伝するべき内容が変われば処分されることも多いです。
また、店舗の外で風雨にさらされるため劣化が激しいため数ヶ月に一度は買い替えが必要な消耗品でもあります。
そのため、しっかりした生地ではなく安価なものが選ばれる傾向にあるというわけです。
一方、旗は薄手のものから非常に厚手のものまで幅広く存在します。
特に会社やチームを象徴する旗にはある程度予算をかけ、しっかりした生地の豪華なものを作るケースが多く見られます。
意外と知らないのぼりと旗の歴史

のぼりや旗の原型となったものは世界中に存在しますが、紀元前12世紀頃の中国にはすでに旗が使われていたと言われています。
その後、国や団体の象徴や遠くからでも視認できる情報伝達手段として、儀式や戦争の場を中心に使われ続けてきた旗は、日本でのぼりとして独自の進化を遂げることになります。
のぼりの歴史①弥生時代〜平安時代
日本の歴史で最も古い旗についての記述は、「魏志倭人伝」の中にある「魏の国から邪馬台国の卑弥呼に旗を贈った」という内容であるとされています。
その後奈良時代・平安時代と時代が移る中で、旗は武家が戦のときに敵方と味方を区別するためのものとしても使われるようになってきました。
平安時代に主に使われていた「流れ旗」は縦長の形であったものの、上辺のみを竿にとめつけて使用するものだったようです。
のぼりの歴史②戦国時代
戦国時代に入ってますます各地で戦が頻発するようになると、現在の形ののぼりにかなり近いものが登場します。
流れ旗では風の影響を受けて文字が見づらくなってしまうため、上辺と左右いずれかの辺を竿に固定した旗が開発されました。
こうしたのぼり状のものに武将の名前や紋章を刻み、家名や戦果をアピールするのに使っていたというわけです。
のぼりの歴史③江戸時代から現代
江戸時代に入って戦が落ち着くと、市井の人々にものぼりが広まりました。
特に商人たちは自分たちの店や商品のアピールのために、目にも鮮やかな宣伝用ののぼりを作ったといいます。
現代でも見られる大相撲の力士の四股名が書かれたのぼりが生まれたのも、このころだったと言われています。
その後も明治・大正を経て戦後を迎え現在に至るまで、のぼりは人々の生活と密着した宣伝ツールとして使われ続けています。
のぼりの宣伝効果は?

街を歩くと、さまざまな店舗の宣伝用のぼりが目にとまります。
パチンコ店など大量ののぼりが店を取り囲むように立ててある様子もよく見られますが、のぼりによる宣伝効果は実際のところどのようなものなのでしょうか。
ここでは、のぼりの宣伝効果についてみていきましょう。
のぼりは顧客とお店との接触機会を増やす便利ツール
のぼりは、道行く人や車を運転している人にお店を宣伝できる広告手段です。
お店の看板などにプラスしてのぼりを立てていることによって人目を引き、お店の存在をアピールできます。
また、のぼりは「単純接触効果」を得るのに最適なツールでもあります。
単純接触効果とは、あるものに繰り返し接すると自然と好印象を抱くようになるという心理効果のことです。
たとえば、毎日通る道にあるお店にのぼりが立ててあったとしましょう。
何気なく通勤・通学をするだけで通行人はのぼりを目にすることでいつの間にかお店やキャンペーンに興味を抱き、好ましい気持ちになってしまうというわけです。
工事不要!安価で設置できるのぼりは費用対効果が高い
のぼりは、非常に安価で設置できます。
野立て看板やデジタルサイネージなどは設置に工事が必要になるため必然的にかかる費用が高く、小規模なお店ではなかなか導入に踏み切れないというケースも多いでしょう。
一方のぼりは1枚1,000円台から作成でき、工事も不要なため納品されれば即日設置が可能です。
気軽に宣伝・集客を行いたい場合は、のぼりは非常に費用対効果の高い広告手段であると言えるでしょう。
宣伝効果のあるのぼりの作り方

安く、気軽に設置できる宣伝用ののぼりですが、あるポイントを抑えるだけで宣伝効果が数倍にも跳ね上がります。
ここでは、のぼりを導入するならぜひ知っておきたい宣伝効果の高いのぼりの作り方について解説します。
デザインにこだわる
店先に掲げるのぼりはお店の顔。
のぼり制作では、お店の外観やコンセプトに合致したデザイン作りを心がけることが大切です。
おしゃれなカフェに和風の筆文字のデザインでは似合いませんし、大衆的なラーメン屋さんに洗練されすぎたシンプルなデザインののぼりではインパクト不足です。
自分の店舗の雰囲気やアピールポイントをきちんと押さえ、お店の雰囲気が伝わるようなデザインを目指しましょう。
統一感を意識する
複数ののぼりを並べて設置する場合は、のぼり同士の統一感を意識するのも重要なポイントです。
色やデザインを統一することで同一の店舗の宣伝だということが一目でわかり、遠くからでも認識しやすくなります。
のぼりのアピール力を高めるためにも、同じ色味や系統立てたデザインを取り入れましょう。
のぼり設置のおすすめポイント

せっかく優れたデザインののぼりを作っても、設置方法によっては宣伝効果が半減してしまうことも。
のぼりを設置する際に押さえておきたいポイントについてもみていきましょう。
複数本をまとめて立てる
まとまった予算があるなら、同じ内容ののぼり複数本をまとめて設置するのがおすすめです。
同じ内容ののぼりがずらりと並んで立っているとそれだけで通行人にインパクトを与え、よく目立ちます。
のぼり同士の間隔は1.8mほどが最も視認しやすく、効果的であるとされています。
常にきれいな状態をキープする
のぼりは、常にきれいな状態をキープしておきましょう。
屋外で風雨にさらされるのぼりは、意外と汚れやすいものです。
汚れたのぼりは清潔感がなく、お店への印象を悪くしてしまうことも。
定期的に洗濯するか、消耗品と割り切って新しいものを発注するのがおすすめです。
定期的に新しい内容のものに取り替える
ずっと同じ内容ののぼりを設置し続けると、通行人は飽きてしまいます。
キャンペーンの切り替え時期などのタイミングでのぼりの内容も定期的に新しくすることで人目を引き、お店への注目度が高まります。
激安!お店ののぼりを作るならUP-T!

お店ののぼりを作るなら、ぜひUP-Tにお任せください!
UP-Tなら、デザイン作成から発注まですべての工程をWeb上で完結できるうえ、激安価格で高品質なのぼりを作成できます。
UP-Tののぼり旗は、ほとんどの注水団やポールに対応できる定番サイズの「レギュラーのぼり (600mm x 1800mm)」、一回り小さい「スリムショートのぼり (450mm x 1500mm)」など、サイズ展開も豊富。
どちらもポリエステル100%の生地で、薄いのに丈夫で風にもよくなびき、裏面への色抜けの良いところが特徴です。
また、ポールへの固定部である乳テープも込みで通常の仕様となりますので、無料でお付けいたします。
のぼりを作りたいけれど業者選びで迷っているという方は、ぜひUP-Tをご検討ください!
まとめ:のぼりと旗の違いは用途と形状

この記事では、のぼりと旗の違いや双方の歴史の他、のぼりの宣伝効果や設置の際に気をつけたいポイントなどについて解説しました。
のぼりと旗の違いは、用途や固定部の数、素材などで、のぼりは旗に比べて風になびきにくく、書いてある文字が読みやすいように改良されているということがわかりました。
のぼりは屋外宣伝のツールとして費用対効果が高く、小規模店舗から大規模な商業施設に至るまで取り入れやすい宣伝方法であると言えます。
「のぼりを導入したいけれど、初めてで不安…」という方は、格安・高品質・充実サポートのUP-Tをぜひご検討ください。